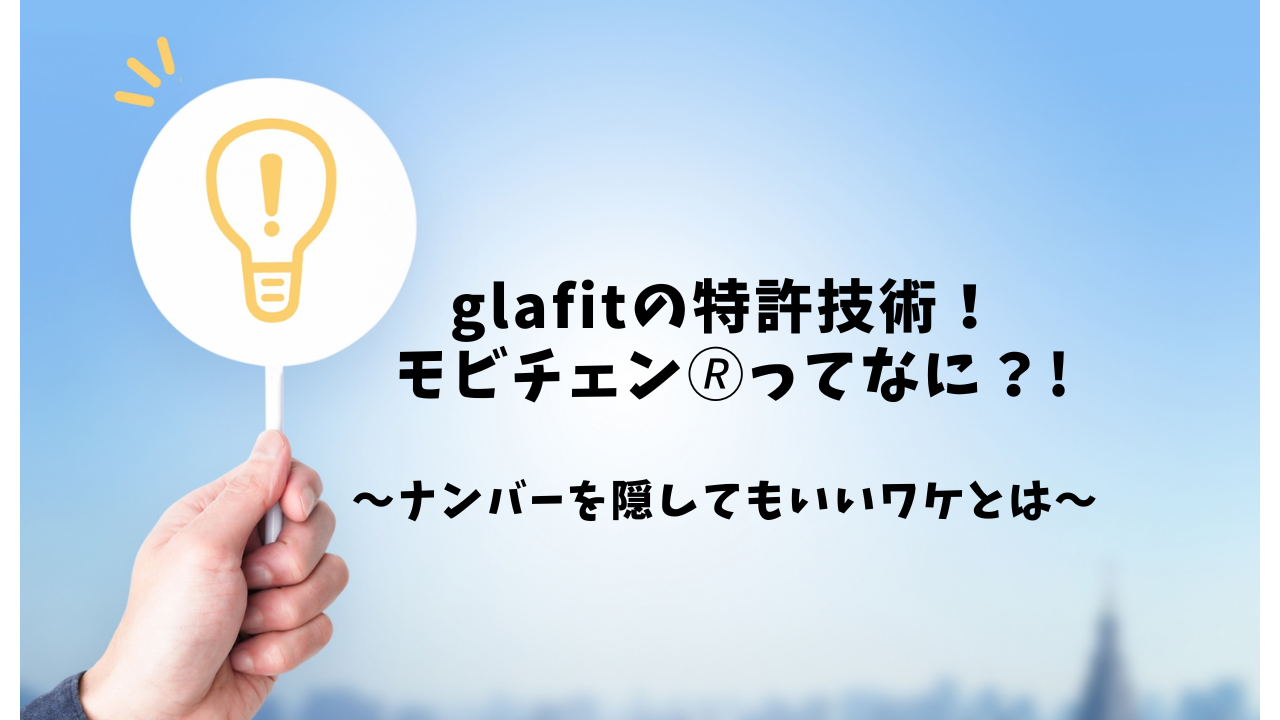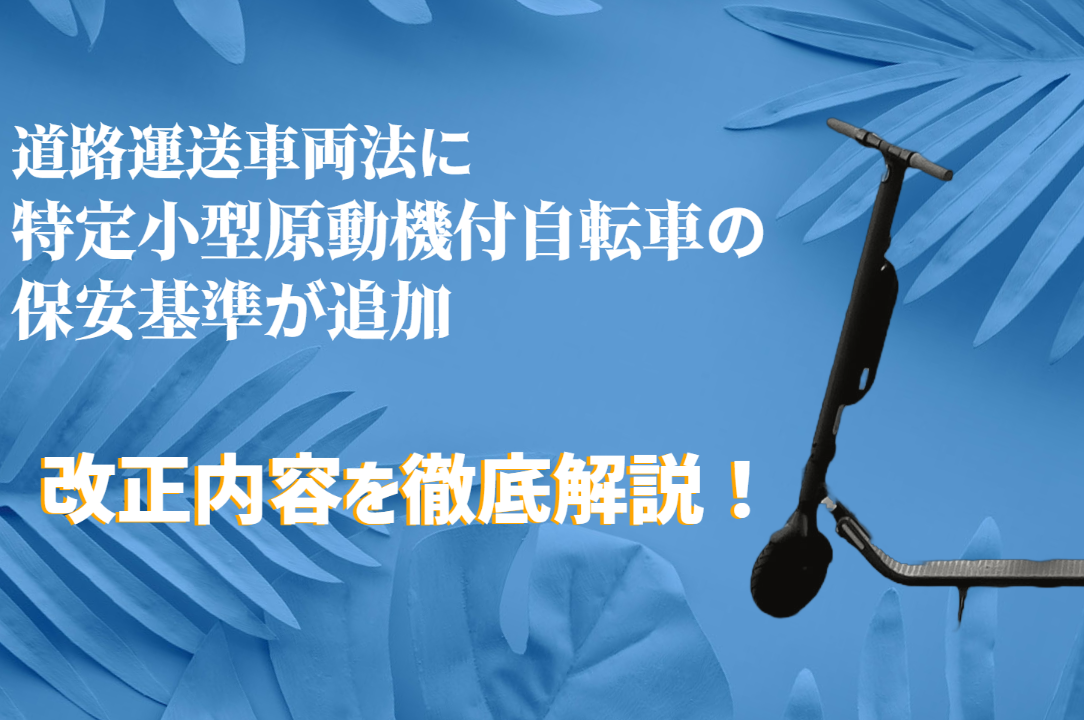目次
電動キックボードを楽しむためには、安全対策が必須です。中でも重要なのが、自賠責保険への加入です。電動バイクも同様、公道を走る際にはさまざまな制約があるため併せてご紹介していきます。
この記事では、電動キックボードと電動バイクにかける保険の種類やその理由についてわかりやすく解説しています。是非最後までご覧ください。
電動キックボードで自賠責保険への加入は必須?

近年、手軽な移動手段として人気が高まっている電動キックボードや電動バイク。しかし、便利な反面、事故の発生リスクも高まっており、安全対策が重要になっています。
電動キックボードや電動バイクの自賠責保険の加入は義務
特に重要なのが、自賠責保険への加入です。
自賠責保険は、交通事故を起こした際に被害者に損害賠償するための保険で、電動キックボードや電動バイクを含め公道を走る全ての自動車・バイク・原動機付自転車において加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入していない状態での運転は罰則対象
自賠責保険に加入していない状態で電動キックボード又は電動バイクを運転すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に加え「道路交通法違反で免許停止処分(違反点数6点)」が科せられます。
2023年6月1日から自賠責保険証明書の電子化も認められている
従来、自賠責保険に加入対象の乗り物は運転時に自賠責保険証明書を携行する必要がありました。しかし、電動キックボードのように構造上収納スペースが限りなく制限されて「紙」での携行が困難な乗り物も存在します。
この問題に対応するため、国土交通省は2023年6月1日より電動キックボードなどの構造上の制約がある乗り物において、自賠責保険証明書の電子保管を認めました。
自賠責保険証明書の不所持だと30万円以下の罰金となりますが、あらかじめ電子化(デジタル化)し、証明書の電磁的記録(写真等)をスマートフォン等に保存しておくと不所持のリスク軽減にも繋がるでしょう。(参照元:令和五年国土交通省令第七号より)
もし加害者が自賠責保険に加入していなかったら?

電動キックボードや電動バイクで運転中に事故を起こした場合、もし自賠責保険に加入していなければ被害者への賠償金を全額事後負担しなければなりません。人身事故の損害賠償額は数千万円から億単位になることもありますので、支払い不能に陥る可能性が高いです。
支払いできずに国が代わって被害者に損害のてん補を行った場合、損害賠償責任者に対して求償します。さらに、被害者が国民健康保険などの各種社会保険を利用した場合にも関連省庁から求償されます。
つまり、自賠責保険に加入していないと、以下のようなリスクがあります。
- 多額の負債を抱える可能性がある
- 国家機関から厳しい追徴を受ける可能性がある
- 将来の人生設計が大きく狂う可能性がある
自賠責保険は、加入が義務付けられているものです。 万が一の事故に備えて、必ず加入しておきましょう。
自賠責保険の加入後に注意すること
電動キックボードや電動バイクに乗る人は、「自賠責加入ステッカー(保険標章)」を確認するなど、自分で自賠責保険の期限を認識しておくことが大切です。
「自賠責加入ステッカー(保険標章)」は、ナンバープレートに貼ってある自賠責保険の満期となる年月を示すものです。
電動キックボードや電動バイクの運転時は、必ず「自賠責加入ステッカー(保険標章)」を定位置に貼り、自賠責保険の加入証明書を携行、もしくは電子化しスマートフォン等に保存しておくようにしましょう。
国土交通省では、街頭取締り、監視活動、無保険車を見つけた場合に通報してもらう窓口を設置するなど、無保険車対策を積極的に実施しています。
自賠責保険に入らなくてもバレないだろうといった気の緩みや甘い考えは禁物です。
自賠責保険、加入する方法は?
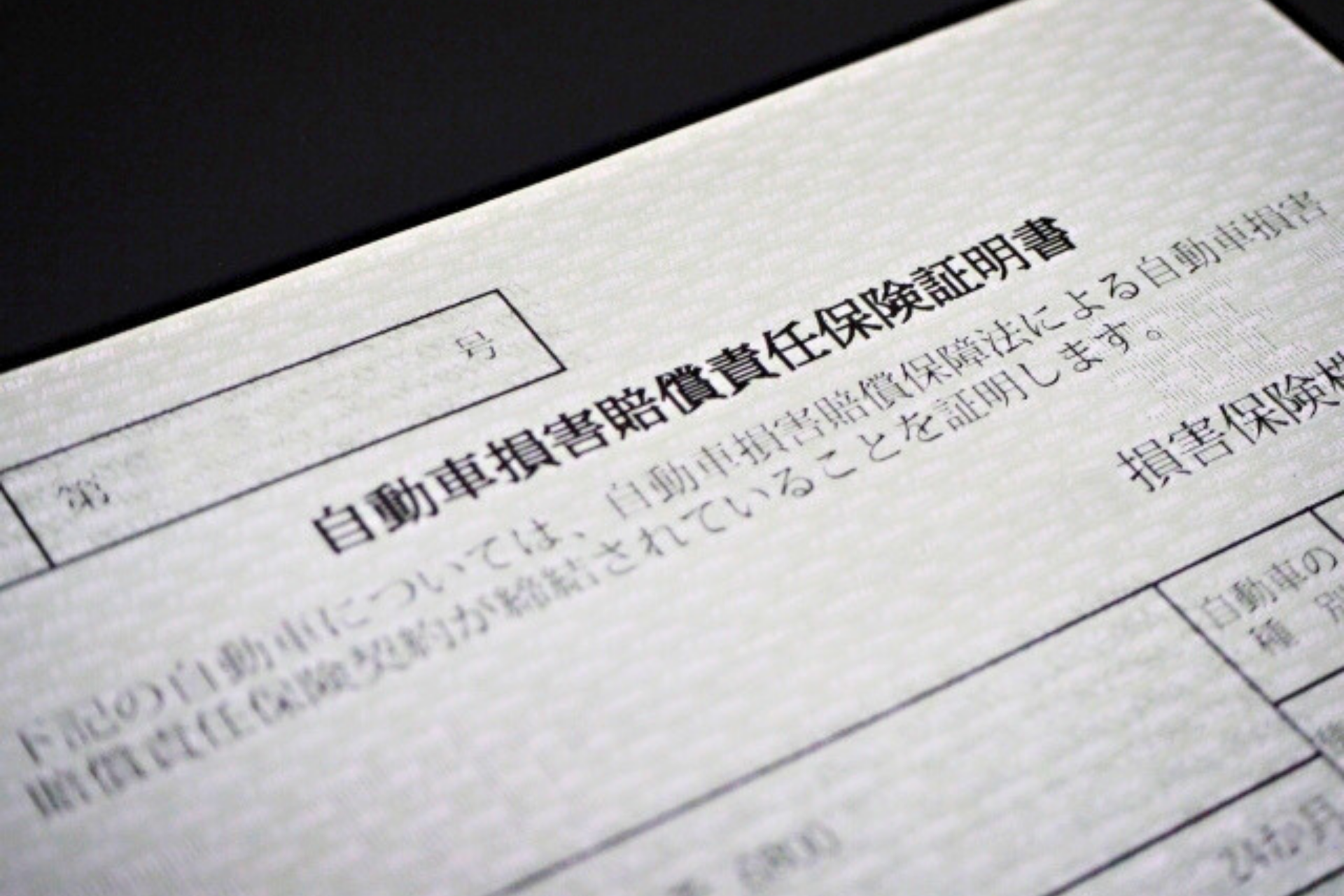
電動キックボードや電動バイクに乗るには、必ず加入しなければならない自賠責保険。加入する方法を以下でご紹介していきます。
加入手続きできる場所
自賠責保険の新規加入手続きは、簡単かつ短時間で済みます。加入手続きは、保険代理店や保険会社の営業所で行います。
他にもバイクや車の販売店、ディーラーやカー用品店、修理工場なども保険代理店となっているので、身近な店舗での加入手続きも可能です。
さらに、自賠責保険への加入は原付・排気量250cc以下のバイクであればコンビニで即日でステッカーを受け取れます。
ただし、ナンバー登録後でないと自賠責保険への加入手続きは出来ないため注意してくださいね。
一般原付タイプに乗るために必要な手続きは、記事「初心者必見】知っておくべき8つの原付ルールを徹底解説!」をご確認ください。
自賠責保険加入に必要なもの
自賠責保険に加入するために、ナンバープレート番号や車台番号など契約情報が分かるもの と、保険料が必要となります。
加入申請すれば手続きが完了し、加入を証明する自賠責保険証明書が発行されます。
ただし、ガソリンスタンドやインターネットでの申込の場合は、自賠責保険証明書が即日発行されないこともあるので、注意が必要です。インターネットで申し込んで、まだ自賠責保険証明書が手元にない場合は、電動キックボードや電動バイクに乗らないよう注意してください。
2024年4月から自賠責保険料金が改定
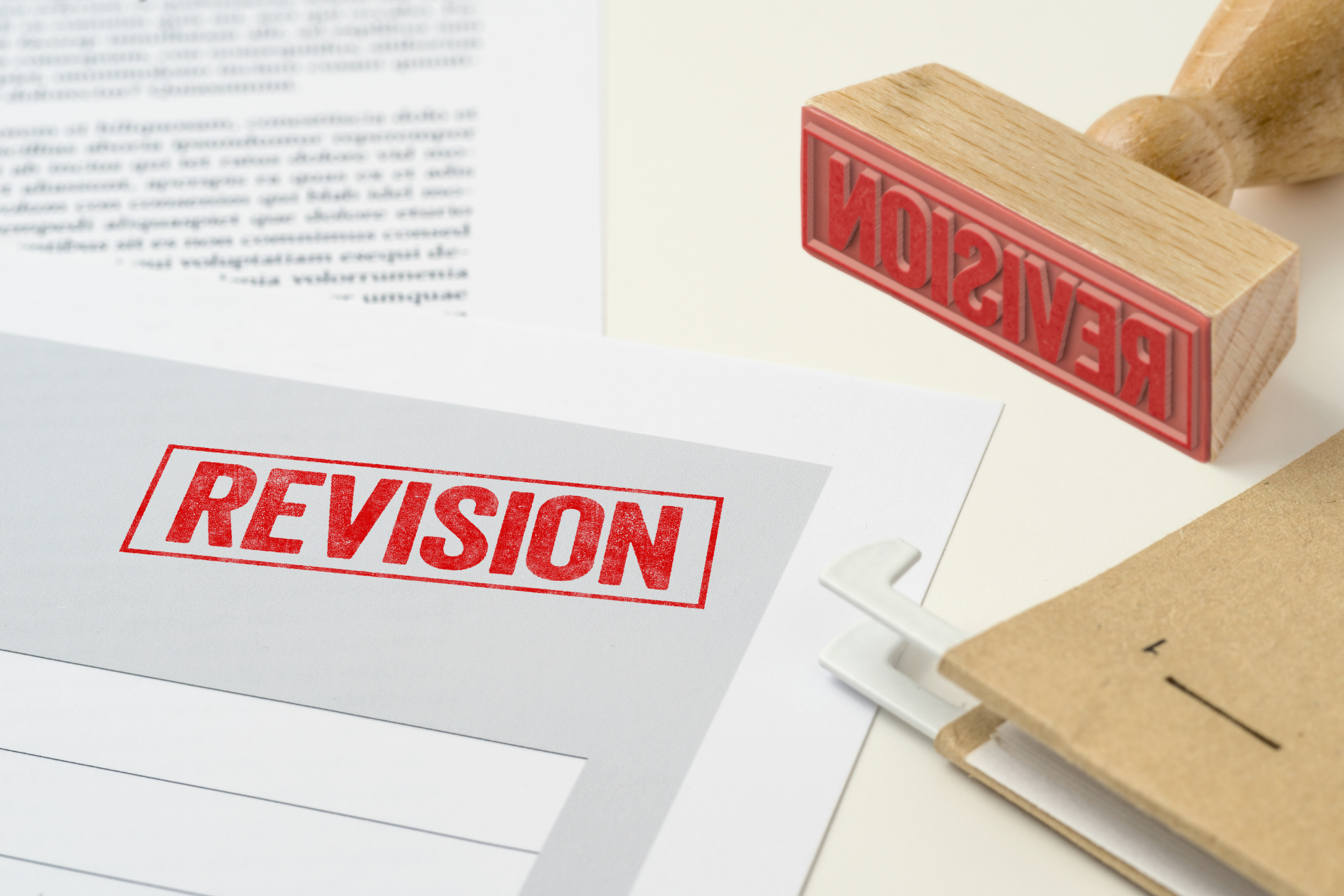
2024年4月より、自賠責保険に特定小型原付の保険料区分が新設されることになりました。どのような変更点があるか、以下で解説していきます。
特定小型原付区分の新設
2023年7月1日の道路交通法改正によって新たに「特定小型原付」区分が新設され、今年には保険料も新たな区分が設けられることから、以前よりも所有者の保険料負担が減ることが期待できます。
一般原付と特定小型原付の金額は?
自賠責保険料は損害保険料率算出機構が定めており、国が金額を定めているためどこの保険会社で加入しても同じ金額です。
| 12か月契約の金額 | 本土地域 | 離島地域(沖縄県を除く) | 沖縄県 | |
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 一般原動機付 | 6,910 | 5,410 | 5,410 |
| 特定小型原付 | 6,650 | 5,400 | 5,400 | |
参照元:損害保険料率算出機構[2024年1月届出PDFデータ]
特定小型原付の自賠責保険料は4〜10%引き下げられ、この料金改定により電動キックボードの利用がさらに促進されることが期待されます。
これまで「特定小型原付=電動キックボード」というイメージが強くありましたが、glafitは2024年3月14日(木)に電動サイクル『NFR-01Pro』を発表いたしました。
現在期間限定で先行販売を受け付けております。気になる方は是非「【免許不要の原付】電動アシスト自転車を超えるglafitバイクNFR-01Pro」をチェックしてみてくださいね。
一般原付と特定小型原付の区分について電動キックボード法改正!2023年7月1日からの新ルールを解説!で詳しく書いていますので、是非そちらもご覧ください。
保険料返還の可能性も
新たに設定される特定小型原付の保険料が現行の原動機付自転車の保険料よりも安い場合、以下の条件を満たすご契約に対して、保険期間や契約開始日等に応じて、一部の保険料が返還される可能性があります。
対象契約
- 保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約
- 車種区分が原動機付自転車の契約
- 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
上記の条件を満たす場合、自賠責保険料の一部が返還される可能性があるため、日本損害保険協会ホームページで詳細を確認してみてください。
電動キックボードにかける保険には2種類ある

電動キックボードや電動バイクにかける保険は、以下のように大きく2種類に分けられます。
自賠責保険
自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、電動キックボードや電動バイクで公道を走る際に加入を義務付けられています。
損害保険会社で契約する自動車損害賠償責任保険、または共済組合で加入する自動車損害賠償責任共済が自賠責保険にあたります。
任意保険
任意保険とは、自賠責保険では補償されない部分を補償する保険です。
名前のとおり「任意」で加入する保険であるため、絶対に入らなくてはならない保険ではありません。
任意保険には入らなくてもいいの?
任意保険は、任意で加入する保険なので、「強制でないのなら入らなくても良い」と考える人もいるでしょう。しかし、任意保険には加入することをおすすめします。
なぜなら、自賠責保険は「事故の被害者を救済することを目的とした保険」であり、自賠責保険の補償の対象となるのは、対人事故の賠償損害のみであるためです。
自賠責保険の補償内容
| 保険の種類 | 補償内容 |
|---|---|
| 自賠責保険 | 被害者のケガや死亡に対する補償 |
| 任意保険 | |
| 被害者の利益逸失の補償 | |
| 加害者である自分のケガの補償 |
|
| 加害者である自分の車の補償 | |
| 保険会社による示談交渉 |
支払限度額は、被害に遭った方1名につき以下のとおりとなります。
万が一、相手が事故で亡くなった場合は、数億円という賠償金が発生してしまうケースもあります。相手が亡くなった場合、自賠責保険の上限は3,000万円なので、もし数億円の賠償金が発生した場合は、3,000万円を超えた分は自己負担しなければなりません。
自賠責保険だけでは補償が不十分な部分を補うのが目的
| 損害内容 | 損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
|---|---|---|
| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) | 最高3,000万円 |
| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 ・ 常時介護のとき:最高4,000万円 ・ 随時介護のとき:最高3,000万円 後遺障害の程度により 第1級:最高3,000万円~第14級:最高 75万円 |
| 傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
任意保険は、自賠責保険では補償されない部分を補償する保険です。対人事故の賠償損害で、自賠責保険だけでは足りない部分は任意保険によって上乗せで補償されます。
任意保険へ加入しないと、事故に遭ったときに自分の補償が一切ない
自賠責保険では、対物事故に対する損害賠償は補償されないため、電動キックボードや電動バイクを運転していて他の車両にぶつかってしまった場合に発生する修理費用や、民家の壁に突っ込んでしまった場合の損害賠償は補償されません。
また、被害対象者の営業活動ができなくなれば、その間の利益逸失の賠償として多額の請求をされるケースもあります。
それだけでなく、自分もケガや後遺障害を負ってしまった場合、自賠責保険では自分のケガや死亡・後遺障害の補償は一切なく、保険会社が示談交渉してくれることもありません。
自賠責保険だけでは、十分な補償があるとは言えないので、自賠責保険に加えて任意保険にも加入しておくのがおすすめです。
まとめ

自賠責保険だけでは、対物事故や自身のケガ、後遺障害などに関する補償が不十分です。そのため、任意保険への加入をおすすめします。
事故やトラブルによるリスクを最小限に抑えるために、保険の加入など適切な対策を講じることが大切です。
安全運転と保険の両面から対策し、電動キックボードや電動バイクの利用を楽しんでください。
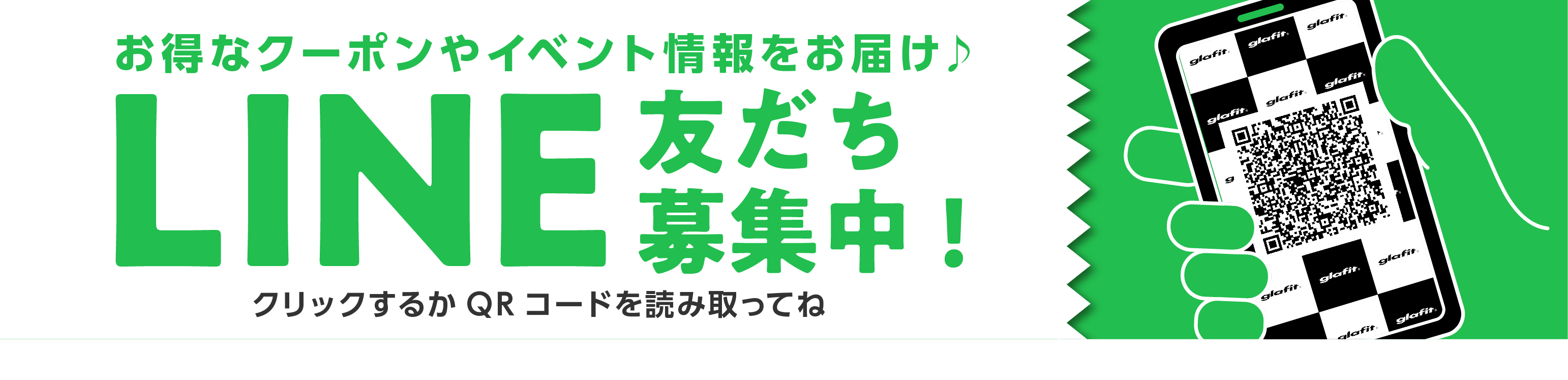
【関連記事】
電動キックボードで坂道の上り下りはできる?(注意点、実証結果あり)
電動キックボード等に特定小型原付区分が新設:免許不要、ヘルメット任意に!
電動キックボード法改正!2023年7月1日からの新ルールを解説!
電動キックボード(一般原付)で通勤は危ない?新しくなった法律や注意点も解説
電動キックボードは電車に持ち込みOK?バスや船での輪行ルール・注意点を解説

一覧へ戻る