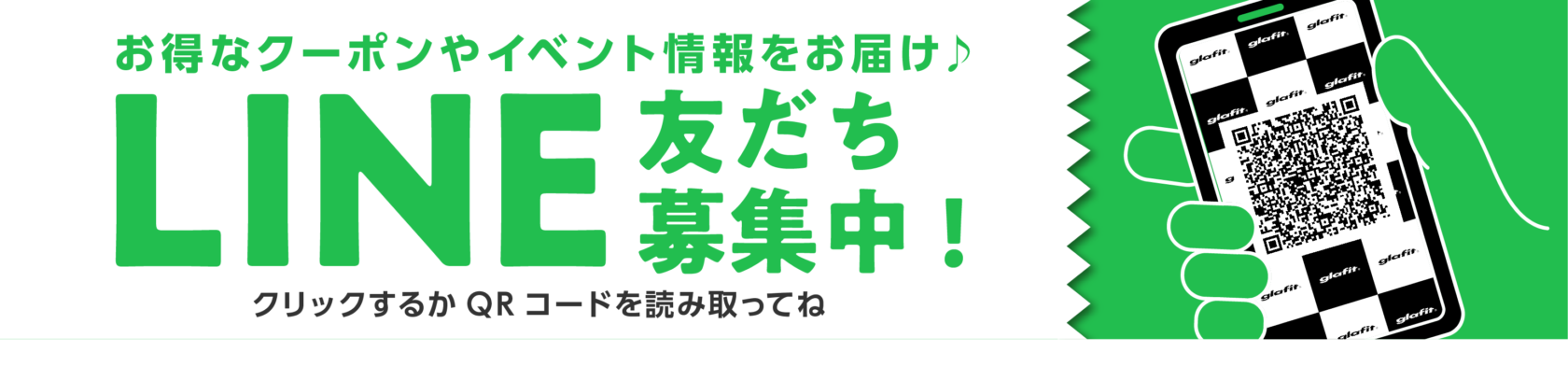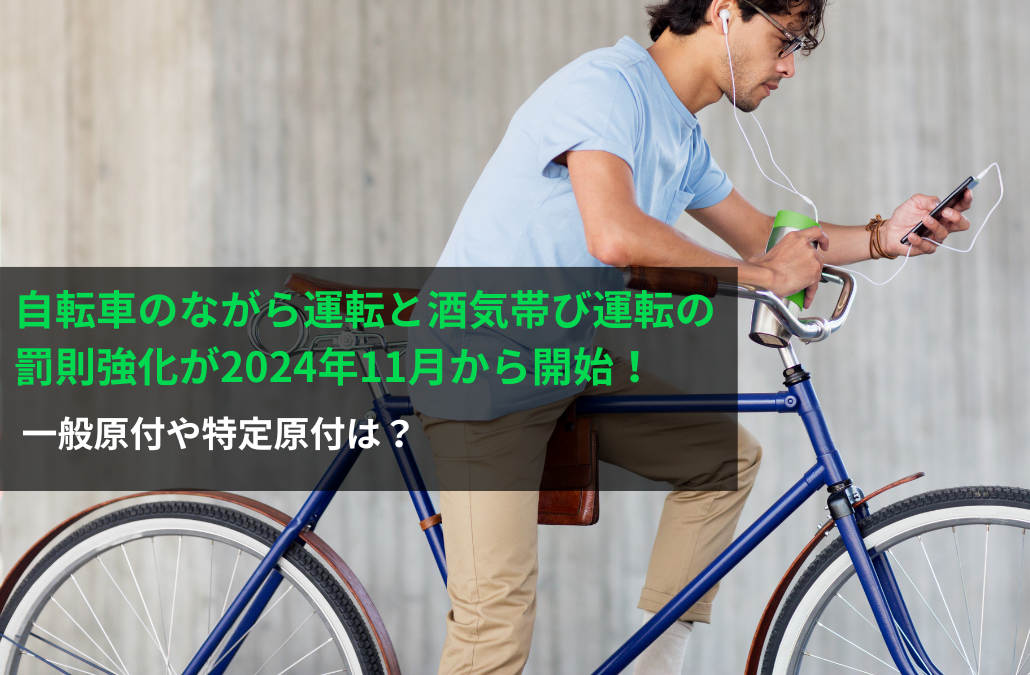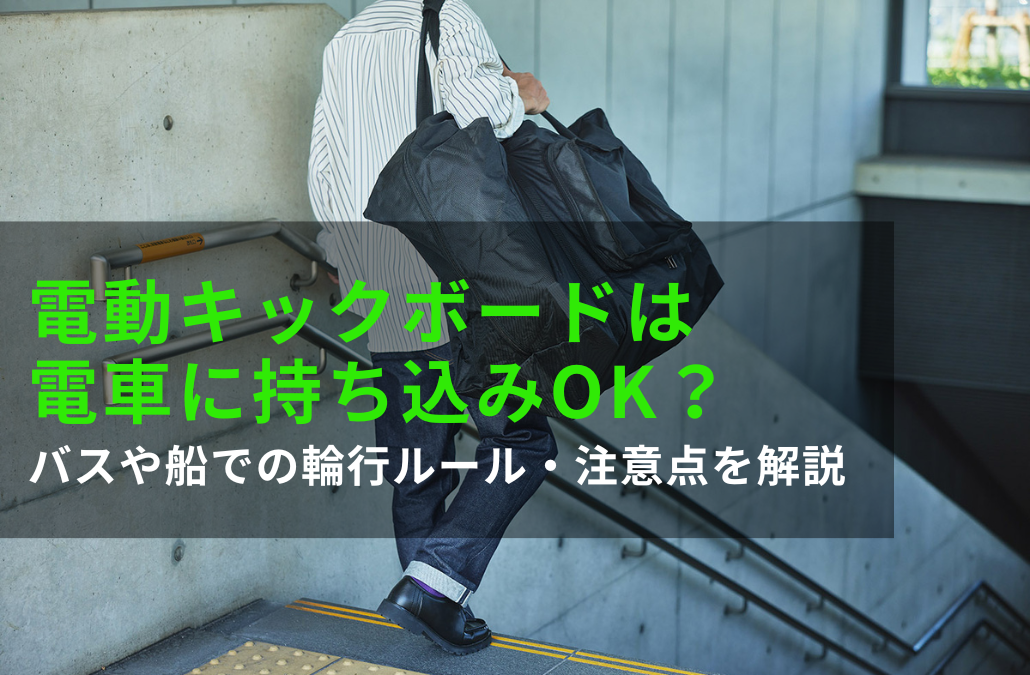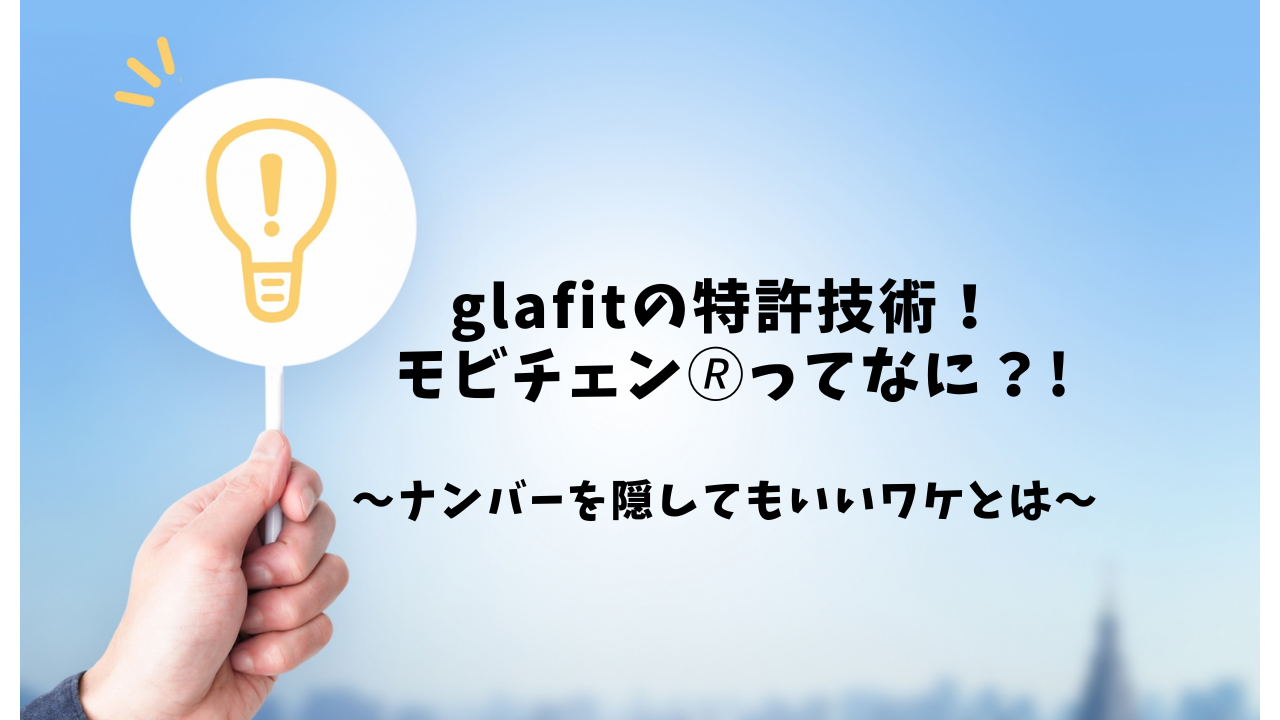目次
2024年11月の改正道交法により、「ペダル付き電動バイクは一般原付である」という事が道路交通法に明文化されました。近年、電動のパーソナルモビリティの普及とともに、ペダル付き電動バイクでの人身事故の急増や全国での違法車両等の摘発件数の増大が問題となってきたために法改正となりました。
今回は、今人気のペダル付き電動バイクを購入する場合に、知っておきたい事前のチェックポイントを3つご紹介します。
それは自転車ですか電動バイクですか?知らない間に違法走行しているかも!?
ペダル付き電動バイクの他、電動モペットやフル電動自転車と呼ばれている
ペダル付き電動バイクは、他にも「電動モペット」「フル電動自転車」などいろいろな呼ばれ方があって、見わけもつきにくいと言われます。このモペットは「MOTOR」と「PEDAL」を組合せた造語「Moped」に由来するといわれています。また、電動アシスト自転車の漕がないものとして「フル電動自転車」と呼ばれたりすることもあります。
ぱっと見た限りではペダルもあり自転車に見えるため、自転車と勘違いして道路を走ってしまう…なんていう事にもなりかねません。これらの呼び方のもの全てが一般原付(以下、原付)に該当しますので、注意が必要です。
勘違いしがちな電動アシスト自転車と原付の違い
ペダル付き電動バイクは、電動モーターを搭載した乗り物です。
ペダルもついていますが、アクセルを装備しペダルを漕がずにモーターの動力のみで走行できます。漕がなくても自走できる機能があるものは全て原付となります。
電動アシスト自転車は「駆動補助機付自転車」となりあくまで”自転車”の扱いとなり、必ず漕がないと進みません。ハンドル周りにスロットルなどのアクセル装置があるものは原付ですので、見分けるポイントになります。
すごく早い電動アシスト自転車もペダル付き電動バイクに該当する
上記で、ハンドル周りにスロットルなどのアクセル装置の有無の確認でアシスト自転車か原付かの区別できるとしましたが、実はもう1点見た目ではわかりにくいですが原付にあたるものがあります。
電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。そのため、ひと漕ぎで急加速する自転車は要注意です。
- 駆動補助機付自転車の基準
アシスト範囲:時速24キロメートル以上のときは、アシストされないこと - アシスト比率(人の力に対する電動モーターが補う力の比率)
時速10キロメートル未満の時、最大で1対2
時速10キロメートル以上24キロメートル未満の時、速度が上がるにつれアシスト比率が減少
その他、詳細は道路交通法施行規則第1条の3を参照
海外から輸入されたものはこのアシスト比率が守られていないことが多く、ペダルしかないものだと自転車にか見えないため非常にわかりにくいのも事実です。
もしあなたが原付ではなく電動アシスト自転車を購入したい場合は、「型式認定TSマーク」が表示されているものを購入すると安心です。電動アシスト自転車の型式認定に合格していることを示しています。
参考:駆動補助機付自転車に係る型式認定品について
アクセルを使わずにペダルを漕いでいるだけの時も原付扱い
これもよく勘違いされていますが “電池がなくなったのでアクセル操作はせずただ漕いでいるだけ” の時は自転車だと思っている人が多いですが、この状態の時でも原付としての交通ルールが適用されますので、間違って歩道を走ってしまうような事が無いよう注意しましょう。
関連記事:
フル電動自転車とは電動バイクのことでペダル付き原動機付自転車だった!
ペダル付き電動バイクを公道で走行するには?
保安基準を満たしている車両を購入しよう
ペダル付き電動バイクは原付になるので、原付の保安基準を満たしているものを購入しましょう。そもそも保安基準を満たしていないバイクで走行すると、整備不良車両運転となり罰則対象になります。
具体的な保安基準は
- 後写鏡(ミラー)
- 警音器(クラクション)
- 前照灯(ヘッドライト)…常時点灯が必要でスイッチでのONOFFはNG
- 独立2系統物理ブレーキ(ディスクブレーキやドラムブレーキ)…また停止までの距離などの細かい規定もあります
- 方向指示器
- 後部反射器
- 速度計
- 尾灯
- ブレーキランプ
- ナンバー灯
などが備わっていないといけません。購入時にはこれらの装備が備わっているか確認しましょう。
性能等確認制度の創出
これまで、原付は任意での型式認定制度の運用のみでした。型式認定は非常に時間と費用が掛かるため、大手メーカーのみが実施してているのが現状です。
2023年に特定原付の車両区分が出来た際に、型式認定以外で車体の保安基準などを国交省管轄で確認する制度が合わせてできました。この型式認定に変わる性能等確認制度を原付にも広げる取り組みが進められています。
今後性能等確認制度ができると、性能等確認済みの車体は保安基準を満たした車両であることが一目瞭然になり、購入時にも判別がわかりやすくなります。
乗るまでにナンバー取得と自賠責保険に入ろう
保安基準を満たしたペダル付き電動バイクを購入しても、すぐには公道走行はできません。公道で乗るには、ナンバー登録と自賠責保険への加入が義務付けられています。
購入時についている「販売証明書」と認印をもち、お住いの役所へ行きます。申請を提出すると無料でナンバープレートとバイクに取付けるためのナットを渡してもらえます。
ナンバープレートは自分で取得が可能ですので、詳しくは下の記事をご確認ください。
原付バイクのナンバーは自分で取得できる!ナンバー取得の流れを伝授します!
ナンバーが取得できたら、自賠責保険に加入します。
既に自動車などを所有していて懇意にされている保険屋さんがあればそちらに依頼いただくくこともできますが、自賠責保険もコンビニなどですぐに加入することが出来ます。すぐに乗りたい!とワクワクしている人は、ご自身でコンビニなどで加入してみましょう。
加入には、登録ナンバーや車台番号が必要になってきますので、ナンバー登録時にもらった用紙を持参するとどちらも記載があります。そのため、ナンバーを取得してから自賠責保険加入の順番となります。
コンビニの情報端末などで必要情報を登録したら、出力された紙をレジにだし保険料を支払うと保険証書とステッカーをもらう事が出来ます。この時に1つ忘れないでほしいのが、保険料は現金払いのみですので、スマホしか持っていかないと支払いができなくなりますのでご注意ください。
自賠責保険に入らずに人身事故などを起こすと被害者への賠償金を全額事後負担しなければなりません。人身事故の損害賠償額は数千万円から億単位になることもありますので、支払い不能に陥ることが考えられます。
万が一の事故に備えて、できれば任意保険も併せて加入するとよいでしょう。
自賠責保険などについては以下の記事をご確認ください。
電動キックボードの自賠責保険加入は必須!任意保険に入らないとどうなる?
乗車時に守ること
実際に乗車するときにも守るべきルールがあります。
まずは、取得したナンバーに自賠責保険のステッカーを貼り、所定の位置に取付けを忘れずに行ってからになります。
また、原付は免許証が必要ですので、運転の際には免許証を必ず携帯しなければなりません。
同時に保険証券の携帯も義務付けられていますが、自賠責証明書を備え付けることが構造上困難であると認められるバイクや原付については、自賠責証明書の画像データ等をスマートフォン等の端末に保存して携行することにより、備付義務および提示義務とみなすことが出来るようになりました。
実際に走行する際には、原付用のヘルメットの着用義務があります。SGマークなど所定の認められたものを必ず被りましょう。
当たり前のことですが、運転する際には必ず交通ルールを守りましょう。信号無視や歩道走行などは大きな事故の原因になります。上記で説明してきたように、仮に電源を切ってペダルを漕ぐだけで走行している場合でも原付となりますので、歩道の走行はできません。必ず車道の左側を走行しましょう。

法的に認められた電動バイクと自転車を切替え可能なバイクとは?
glafitでは、道路交通法上”1台で電動バイクと自転車を切り替えて利用できる電動バイク”GFR-02モビチェン付きを販売しています。
これまでの説明で、「モーターを用いずに、ペダルのみを用いて走行させる場合も、原付の交通ルールを守らなければならない」としてきてことと矛盾することになっていますが、どうやって切り替えるのでしょうか?

電動モビリティならではのモビチェン機構の開発で得られた「バイクと自転車の切り替え」
glafitでは2018年に創設された「規制のサンドボックス制度」を利用し、電源が切れている状態での利用時には自転車として利用できるようにしたいとして、法改正を要望しました。そこから実証実験の他、警察庁や国交省、総務省等々関係各所と協議を重ねてきました。この協議の中で生み出されたのが「モビチェン機構」です。
2021年6月の警察庁通達*1によって国内で初めて「車両の区分を変化させることができるモビリティ」として認可されました。ナンバーを覆っている状態では自転車として歩道*2や自転車道を、ナンバーを見せた状態では原付としてフル電動でペダルを漕ぐことなく車道を走ることが可能です。

モビチェン。左)電動バイク状態、右)普通自転車状態
警察庁が通達で示した「車両の区分を変化させることができるモビリティ」は以下の項目が要件として定められています。
●人力モード⇔EVモードの切り替えは停止中でなければならない
●人力モードではナンバープレートを非表示とすること
●人力モードでは原付として走行ができない状態であること
●人力モードであることが外観上明らかであること
*1 参考:令和3年6月 警察庁丁交企発 第270号/警察庁丁交指発 第60号
*2 車両の大きさが普通自転車として定められた大きさ以下で、自転車通行可の標識のある歩道に限ります
2025年1月現在、国内ではglafitのGFR-02モビチェン付きだけが、警察庁の通達で切替えを認められています。
販売時には、免許証の確認の他、ナンバー取得と自賠責保険に加入してからでないと納車されない仕組みがとられなど、法令順守で乗ってもらえる仕組みづくりを推進しています。
詳しくは公式ホームページをご確認ください。
電動バイクGFR-02 公式HP
モビチェン開発秘話はこちらから
モビチェンってなに? 電動バイク(原付1種)と自転車を切替えて使う、日本初の二刀流バイクは何故できたのか?
まとめ
近年、その利便性の高さや脱炭素など環境にもよい事などから、電動パーソナルモビリティの普及が加速しています。
一方でその手軽さからなのか、車両であることを忘れ交通ルールを蔑ろにして自分も周囲の人も危険にさらすような利用者を目にすることがあります。
電動バイクも自転車も、自動車と同じ車両であるという認識を持って利用しましょう。
ペダル付き電動バイク(電動モペット)は原付になりますので、無免許では乗れません。無免許でペダル付き電動バイクを公道で運転した場合の刑事処分は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰があります。また、万一人身事故を起こした際に無保険だった場合には多額の損害賠償を追う事になり、過失運転致傷で逮捕される場合もあります。
ペダル付き電動バイクを購入する時には、まず車体が保安基準を満たしたものを選ぶようにしましょう。
また、「自分だけは大丈夫」などと思わずに運転する際は、事故を起こさないよう交通ルールに従って安全運転を心がけるようにしましょう。
関連記事:
原付一種、電動アシスト自転車、特定小型原付を徹底比較!おすすめも紹介
電動バイク・電動キックボードに乗るために必要な免許証とは? 免許証の種類を解説
glafitの特許技術! モビチェン🄬ってなに? ~ナンバーを隠してもいいワケとは~
電動バイクGFR-02を便利に感じるお薦め利用シーン5選

一覧へ戻る