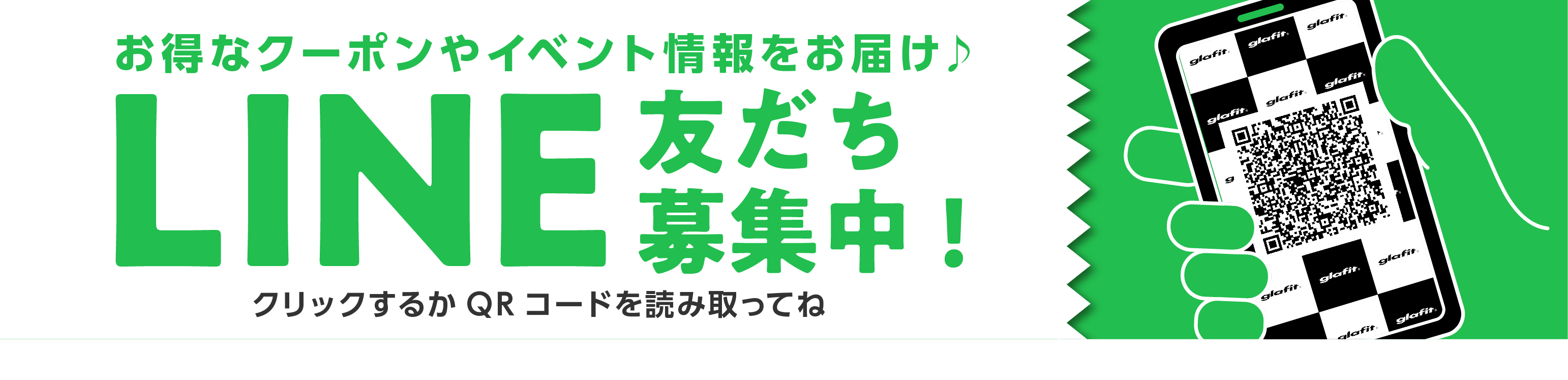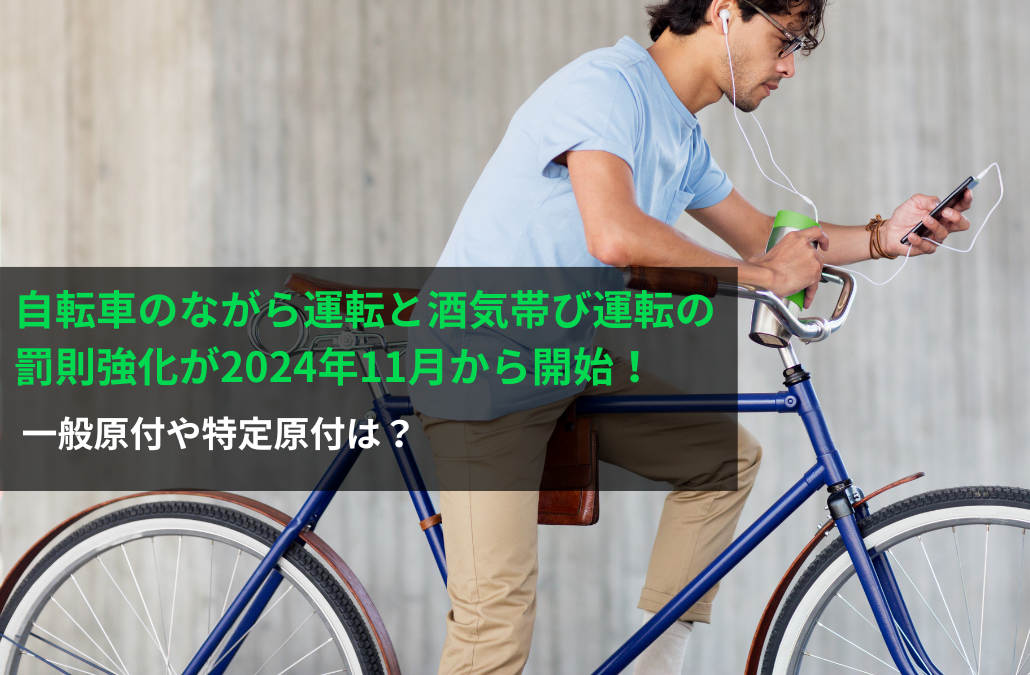目次
自転車のような見た目なのに、ペダルをこがずにスイスイ進む不思議な乗り物を見かけたことはありませんか?最近では、見た目は自転車のようなのに、ペダルをこがずに電動で走るモビリティが増えてきています。これらは法律上、「一般小型原動機付自転車」や「特定小型原動機付自転車」として扱われる新しいタイプの乗り物です。
2025年2月28日に新設された「一般小型原付」は免許が必要で最高速度30km/hまで。一方、2023年7月の法改正で誕生した「特定小型原付」は、16歳以上なら免許不要で乗れる新しい選択肢です。この記事では、より身近な存在となりつつある特定小型原付に焦点を当てて詳しく解説していきます。
特定小型原動機付自転車とは
「特定小型原動機付自転車」は、キックボードタイプの者の他にも、見た目は自転車に近いものの電動モーターの力だけで走行できる小型の電動バイクです。ペダルが付いているモデルでも、基本的にはアクセルをひねるだけで進むフル電動の乗り物として設計されています。※車両の要件として決められています。
従来の電動アシスト自転車との大きな違いは、人力でペダルをこぐ必要がない点にあります。電動アシスト自転車はペダルをこぐ力をモーターが補助する仕組みですが、特定小型原付はモーターのみで走行可能。そのため法律上は「原動機付自転車」として扱われ、自転車とは明確に区別されています。
最大の特徴は16歳以上なら運転免許が不要という点です。これまで原付バイクに乗るには原付免許が必要でしたが、特定小型原付なら免許なしで公道を走行できます。ただし、ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入は必須となっています。
引用:警視庁「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて
特定小型原動機付自転車の法的要件
特定小型原動機付自転車として認められるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
車体仕様の基準
- 車体寸法:長さ190cm以下、幅60cm以下
- 動力:定格出力0.60kW以下の電動機を搭載
- 速度性能:最高速度が時速20kmを超えない(20km/hリミッター装備)
- 変速機構:走行中に速度制限設定を変更できない構造で、オートマチック
- 表示灯:時速20km超の速度が出せないことを示す「最高速度表示灯」を装備
これらの基準を一つでも満たさない場合、見た目がペダル付き電動バイクであっても特定小型原付には該当せず、従来の原付や自動二輪車として扱われます。その場合は運転免許が必要となり、30km/h制限などの従来ルールが適用されます。
参考:特定小型原付、誤解したまま公道走行したらアウト! よくある7つの誤解を徹底解説
年齢制限と免許
特定小型原付は16歳以上であれば運転免許不要で運転できます。16歳未満の運転は法律で禁止されており、年齢確認は購入時やシェアサービス利用時に厳格に行われます。メーカーの販売システムでも16歳以上の確認がないと起動できない仕組みが採用されています。
引用:警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
必要な手続きと維持費用
登録とナンバープレート
免許は不要でも、市区町村役場での登録とナンバープレートの取得は義務です。特定小型原付用の小型ナンバープレート(縦横10cm程度)を交付してもらい、車体の見やすい位置に取り付けなければなりません。ナンバーを取得せず無登録で公道を走ることは違法行為となります。
保険と税金
全ての原動機付自転車と同様に、自賠責保険(強制保険)への加入が義務付けられています。未加入で公道を走ると罰則の対象です。2024年4月以降、特定小型原付向けに専用の保険料区分が新設され、保険料が従来より安価になっています。
年間の維持費として、軽自動車税が年額2,000円と自賠責保険料が発生します。月換算すると数百円程度という非常に低い維持費で済む計算になります。
交通ルールと走行マナー
基本的な走行ルール
原則として、特定小型原付は車道走行が基本です。自転車と同様に道路の左側端に寄って走行し、車線がある場合は一番左の車線を走ります。自転車道や自転車専用レーンが整備されている場合は、そこを通行することも可能です。
歩道や路側帯は基本的に走行できません。ただし、「特例特定小型原付」(歩道通行モードを備えた車両)に限り、「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道で、車体を歩道モード(時速6km以下)に切り替えた場合のみ走行可能です。
安全装備とマナー
特定小型原付の運転者には、ヘルメットの着用が努力義務となっています。法律上は罰則なしの努力義務ですが、万一の転倒や事故に備え、必ず乗車用ヘルメットを着用することが強く推奨されます。
以下の行為は法律で禁止されています:
- 2人乗りの禁止:タンデム(二人乗り)は法律で禁じられています
- 飲酒運転の禁止:自動車同様に厳罰の対象です
- ながら運転の禁止:走行中のスマートフォン操作やイヤホンの大音量使用は違反
引用:警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
glafit NFR-01シリーズの紹介
利用用途に応じて、必要なグレードを選択できる!
NFR-01 Pro + ハイエンドモデル ハイパワー・IoT搭載モデル / NFR-01 Pro ハイエンドモデル IoT非搭載でハイパワーをお手頃価格に
NFR-01 Pro+ は、2023年の法改正に合わせて発売された特定小型原付対応のフラッグシップモデルです。ペダルは付属しますが基本はアクセルスロットルをひねって走るフル電動バイクとして設計されています。
定格出力500Wの強力なインホイールモーターと大容量48Vバッテリーを搭載し、急な上り坂でもペダル不要でグイグイ進むトルクを実現。最高速は法定の20km/hですが、その範囲内での加速力・登坂力は特定原付カテゴリー最強クラスを誇ります。
また、最新のIoT技術を備えており、内蔵の4G LTE通信により、スマートフォンの専用アプリから車両データを確認・操作可能。バッテリー残量や走行可能距離、車両の位置情報をリアルタイムで把握でき、NFC(ICタグやSuica等)での鍵の施解錠にも対応しています。
また、NFR-01 Proは、車両の基本スペックはそのままですが、IoTのスマートロック機構のみを取り外したモデルになっています。坂道などの登坂力は欲しいけれど少し費用をおさえたい方向けになっています。
製品紹介ページ:glafit NFR-01 Pro
NFR-01 Lite – 手頃で日常向きなモデル

NFR-01 Liteは、Proの機能をシンプルにして価格を抑えた普及モデルです。車体デザインや基本構造はProと共通ですが、バッテリーが36V・7.8Ahとやや小型で、モーター出力も350Wにチューニングされています。
価格は約187,000円(税込)と求めやすく、**「電動モビリティ初心者にちょうどいいスペックと価格」**を実現。満充電あたりの走行距離は約33kmで、日常の通勤・通学や買い物には十分な距離をカバーします。
Liteももちろんアクセルだけで走行でき、坂道での登坂能力は約22%勾配まで対応。重量はバッテリー込み約19.5kgと非常に軽量で、ペダルやハンドルを折りたためば室内や玄関にも収納可能なコンパクトさを実現しています。
両モデルとも特定小型原付に適合した車両であり、16歳以上なら免許不要・ヘルメット努力義務で乗れます。モード切替機能により歩道通行モード(6km/h制限)も搭載しており、公道で法律を守って安全に走行できるよう設計されています。
製品紹介ページ:glafit NFR-01 Lite
ガソリン不要でここまで安い!毎日使える節約モビリティ
特定小型原付の大きな魅力は維持費の安さです。ガソリンを使わない電動バイクのため、燃料代は電気代のみ。10km走行しても電気代は約3.5円程度で、同等の原付ガソリン車の燃料費(約36円/10km)と比べて1/10以下という経済性を実現しています。
自宅で充電できるため、ガソリンスタンドに行く手間も不要。満充電にかかる時間は4~6時間程度で、一晩コンセントにつないでおけば翌日の通勤分は十分に補充可能です。
通勤・買い物・シニアも!ひろがる活用シーン
通勤・通学
混雑する電車や渋滞するバスに代わり、ドア・ツー・ドアで移動できる手軽な通勤手段として注目されています。片道5〜10km程度なら、20km/h制限でも30分前後で到着でき、時間が読めるのも魅力です。
シニアの移動手段に
免許返納後の“次の足”としても活用されており、坂道も体力に頼らずスムーズに登れることから、電動アシスト自転車では不安を感じる方にも支持されています。
買い物・近所のちょい乗り
自宅近くの買い物や用事、ちょっとしたお出かけに便利。車よりも取り回しがラクで、駐輪スペースも確保しやすいため、都市部での利用にも適しています。
家庭内のサブモビリティ
車が1台しかない家庭で、「ちょっと出かけたいときのセカンドモビリティ」としても活用されています。折りたたみ式のモデルなら玄関先でも収納しやすく、省スペースで置けるのも利点です。
ビジネス用途にも
営業回りなど、短距離の業務用モビリティとしてもオススメ。維持費が安く、車両登録や駐車スペースの負担が少ない点も選ばれる理由です。
まとめ
特定小型原動機付自転車は、自転車の手軽さとバイクの動力を併せ持った新しいモビリティです。16歳以上なら免許不要で乗れる利便性と、年間数千円という低い維持費により、多くの人にとって身近な移動手段となりつつあります。
ただし、法律上は原動機付自転車であることを忘れてはいけません。ナンバー登録、保険加入、交通ルールの遵守は必須です。特に歩道走行の禁止、2人乗りの禁止、飲酒運転の禁止など、違反行為には注意が必要です。
適切な手続きを経て、安全運転を心がければ、特定小型原付は日常生活を大きく変える便利な乗り物となるでしょう。環境に優しく、経済的で、手軽に使える新しい移動手段として、今後さらなる普及が期待されています。

一覧へ戻る